子育て中にふと孤独を感じてしまうことはありませんか。
子育てをする中で誰かに相談できずに悩んでいる方が年々増加しているように感じます。
特に地方在住で頼れる人がいないそんな状況で乳幼児の育児に奮闘するママさんたちはどんな思いで子育てをされていますか。
現在、日本では【核家族化】が進んでいます。
私の家族も核家族のアパート暮らしだった時期があります。
良い意味で誰に気を遣うことなく不自由なく暮らせましたが、その反面で苦労も多々ありました。
妻はあまり口には出しませんでしたが、不安で辛かった時も多々あったのではないでしょうか。
昔の頃とくらべると私たちを取り巻く環境というのは子育てというところだけで切り取ったとしてもその環境は大きく変化しているのではないでしょうか。
かつての大家族とは異なり今では両親だけで子育てを担う時代に流れていっています。
この記事を読んでその現状と課題、そしてその課題に対する解決の一助になれば幸いです。
日本の核家族化の現状
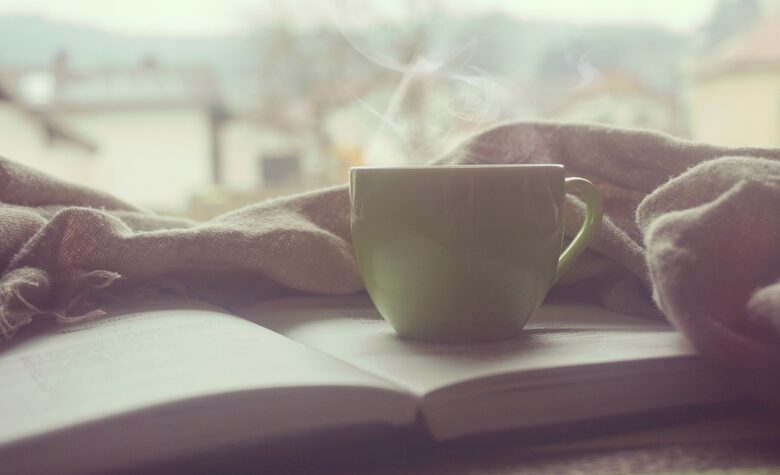
日本では高度経済成長期を経てまもなく少しずつ核家族化が進んできたようです。
ある統計によると、児童のいる世帯のなんと約7割強が核家族となっているという結果がでているようです。
これはわずか数十年前と比べても大きな変化です。
核家族化が進んだ背景にはいくつかの要因があると言われております。
- 就職や進学のために、若い世代が地方から都市部へ移動。
- 価値観の変化:個人のライフスタイルを重視する傾向の増加。
- 住宅事情:都市部での狭小住宅の増加。
- 女性の社会進出:共働き世帯の増加。
これらの要因が複合的に作用して現在の核家族中心の社会構造が徐々に形成されてきたと言われております。
皆さんの中にも
「確かに、私もそうだな」
と思われる方も多いのではないでしょうか。
私はこの背景をみたときにある意味では日本はとても豊かな国に成長を遂げているし、もっと新しい道に進んでいくのであろうと感じました。
一方ではその影響で古き良き日本の子育てにおける価値観の変化がやや悪い方向で作用しているという事に気づくことができました。
まず自分たちを取り巻く環境を理解したうえで、悲観的ならず小さくても良いのでできることから始めることが大切なのかなと思いました。
核家族における子育ての課題

では次に核家族における子育てについての主な課題について詳しく考えてみましょう。
核家族では育児の負担は特に母親に集中する
乳幼児をもつお子さまのお父さんお母さんの親世代、両家の親戚などからの日常的なサポートが得られにくいので基本的には1日中お子さまの育児に疲れ果ててしまうケースが少なくありません。
お母さんが夜中の授乳で眠れず昼間も家事に追われ休む暇がありません。
お父さんもお父さんで、家庭の為に一生懸命に働くがゆえに、中々育児のフォローにまで手が回らないのが実情ではないでしょうか。
さらに実家は住まいから遠く離れているため中々頼れずにいて、子育て中のママは不安を抱えて育児をしているという話を良く聞きます。
核家族化におけるコミュニティからの孤立
特に地方在住で周囲に知り合いがいない場合、子育て中のママさんは大変不安になることでしょう。
育児の悩みを相談したり、経験を共有したりする機会が減少することで、不安や孤独感は増大していく傾向にあります。
また、子どもの発達や健康に関する些細な疑問でも気軽に相談できる相手がいないことで、必要以上に心配してしまうことも多々あることでしょう。
核家族化によって親世代からの子育てのコツを教える機会が減少
このことで、育児におけるアドバイスを受ける機会があまりない状態になっています。
昔は祖父母や親戚から直接育児のコツを学ぶ環境が多くありましたが、現在ではそういった機会自体が減少しているように見受けられます。
その結果、初めての育児に戸惑い不安を感じるお父さんお母さん方が増えているといいます。
「こんなときどうすればいいの?」
「これで合っているのかな?」
といった不安が常につきまとうことも核家族化の1つの課題と言えるでしょう。
私も経験がありますが、さっきまで元気にご飯を食べていた子どもが急に具合が悪くなり、嘔吐と発熱に陥ってちょっとしたパニックに陥りました。
そういった時にすぐに助けてもらえるパートナーや仲間、コミュニティなどを構築するリスク分散のような考え方が昔よりも大切になっていると感じました。
核家族での子育てを乗り越えるための提案

ここまで核家族での子育てにおける現状とその課題について見てきました。
確かに多くの課題がありますが、悲観ばかりしてしまうと先に進むことができません。
これらの課題に対する解決策を考え、提案できればと思っています。
提案その1 地域のサポートネットワークを活用する
まず、お住まいの地域に子育てに関するサポートネットワークがあるかどうかを確認しましょう。大なり小なりそれなりの組織が存在するはずです。
そして、サポートネットワークを積極的に活用することをおすすめします。
多くの自治体では子育て支援センターや保健センターなどを設置おり、これらの施設では育児相談や親子の交流の場を提供しています。
例えば、子育て支援センターでは同じ年齢の子どもを持つ親同士が出会い情報交換をする機会があります。
最初は少しハードルが高いと感じるかもしれませんが、同じ悩みをもつ方々が集まるはずです。是非検討してみてはいかがでしょうか。
提案その2 オンラインコミュニティの活用
子育てに関するオンラインコミュニティの活用も有効ではないでしょうか。
SNSやママ向けのアプリを通じて、全国の同じ境遇のママたちと情報交換することができます。
時間や場所を選ばずに相談できる点が大きな魅力の1つですし、お子さんが昼寝している時などご自身のペースに合わせて活用することが可能です。
緊急性の高いものには向きませんが、ちょっとした違和感や不安、悩みの種など投稿することで、様々な視点、角度から色々な情報を得ることができるのではないでしょうか。
注意しなければならない事として、妥当性の確認やエビデンスについてはご自身で対応する必要があります。
病気などの重要な判断をする際は必ず専門家に相談するように心がける必要があります。
提案その3 パートナーとの協力体制の構築
子育てにはまず、パートナーとの協力体制がとても重要だと考えます。
まず大前提として、昨今の日本においいて育児は母親だけの仕事ではありません。
まずはこの認識をしっかりとご自身にインストールする必要があります。
一般的な家庭において、お父さんの積極的な育児への参加が、お母さんの身体と心の負担軽減につながります。
最近では企業の方針にも変化がみえており、男性の育児休業制度の活用も積極的に取り入れている会社も増えてきました。
たとえ短期間だとしても、父親が育児に専念する時間を持つことで家族の絆が深まり、その後の家庭生活にも良い影響を与えることができるでしょう。
私自身、子どもがある程度の年齢になったので、乳幼児の子育てにおける企業の支援などの恩恵を受けることはありませんでしたが、非常に良い取り組みだと考えます。
小さなころに子育てにパートナーと共に向き合い、お互いが切磋琢磨していくことで、その後の家庭円満に繋がる1つの要素になりえるのではないでしょうか。
まとめ:一人で抱え込まず、支援を活用しよう

ここまでご覧になって皆さまはどのような印象をお持ちになりましたか。
近年の核家族化における子育ては確かに多くの課題があるという現状を理解する必要があります。
しかし、それは決して乗り越えられない壁ではありません。
地域のサポートやインターネットを通じたオンラインコミュニティ、そしてなによりも一人で悩むまえにまずはパートナーとの協力体制を築く。
これらを上手に活用することで現代における子育ての課題を乗り越えることができるのではないでしょうか。
- 高度成長を経て、様々な複合要因によって日本は核家族化が進んだ。
- 現代の日本における核家族化の課題は育児のおける孤独と不安の解消である。
- 地域サービス、インターネット、そしてパートナーと協力しながら課題を乗り越えていく。
一人ひとりの状況は異なると思います。
でも、必ず自分に合ったサポートの形があるはずだと私は考えます。
一人で抱え込まず、まずは周囲にある支援そしてパートナーである方へ相談しながらお互いにとって良い道を共に作っていきましょう。
子育ては大変なこともありますが、同時にかけがえのない喜びに満ちた時間でもあります。
この貴重な時間をできるだけ楽しく過し、皆さんの笑顔があふれるものになることを心から願っています。
